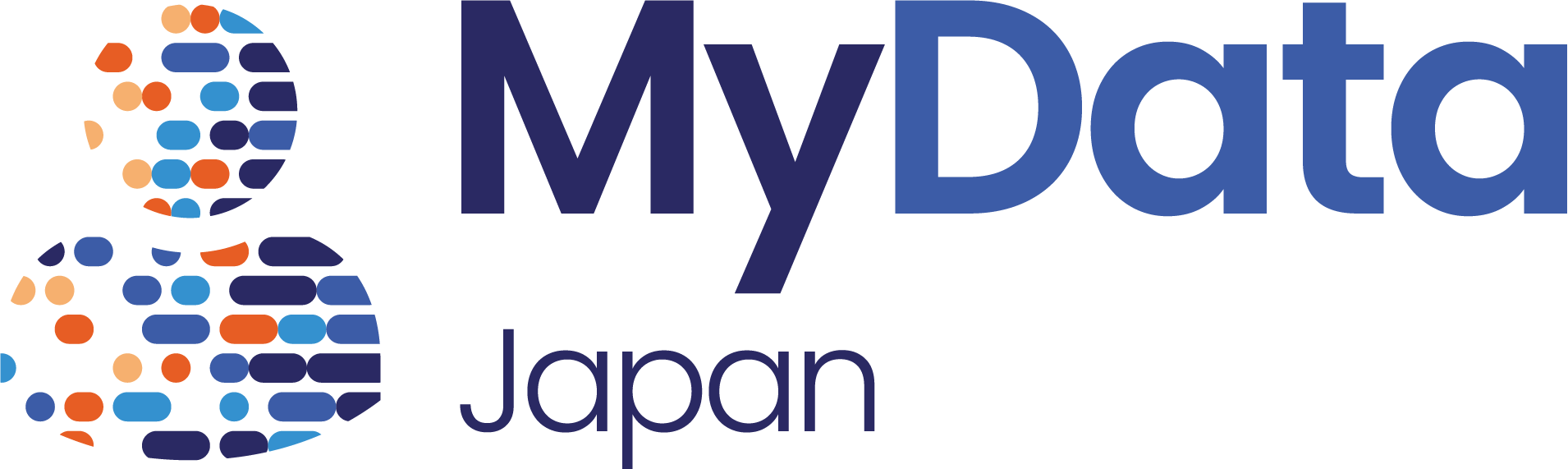案件名:「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に関する意見募集
所管省庁・部局名等:公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室
提出日:2025年6月13日
一般社団法人MyDataJapan 公共政策委員会
東京都港区赤坂8−4−14青山タワープレイス8F
一般社団法人MyDataJapan 公共政策委員会は、公正取引委員会事務総局の「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に関する意見募集について、以下のとおり意見を申し述べます。
1. SPSIへの言及について(363行以下、1010行以下等)
SPSIは、総務省で策定するスマートフォンアプリにおけるベストプラクティスである。その対象は、利用者のプライバシー、セキュリティ、青少年保護であり、スマホソフトウェア競争促進法7条、8条における正当化事由と相当程度重複している。利用者保護の観点から策定されたベストプラクティスの記載事項を、正当化事由において積極的な考慮要素とする指針案の姿勢は、公正競争と利用者保護のバランスに配慮した妥当なものとして高く評価できる。
2.アプリストアに係る指定事業者による行為(476行以下 【想定例8】)
指針案は、広告IDによる追跡に関する表示について、以下のような表示は、指定事業者による「不当に差別的な取扱い」に該当するとする。
「アプリストアに係る指定事業者が、当該アプリストアの利用のための審査等において、スマートフォンの利用者に紐付いた広告ID等の識別子を使用して当該利用者を識別し広告事業に用いる行為について、個別アプリ事業者による当該行為の対象範囲及び態様は同様でありスマートフォンの利用者に係る情報の保護の観点からのリスクに差異がないにもかかわらず、当該指定事業者以外の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関しては当該リスクを強調した否定的な説明からなるポップアップ表示を行うことを条件とする一方で、当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアに関しては安全性を強調した説明からなるポップアップ表示を行うこと。」
もちろん、本当に「個別アプリ事業者による当該行為の対象範囲及び態様は同様でありスマートフォンの利用者に係る情報の保護の観点からのリスクに差異がない」のであれば、表示に差異を設けることは不合理である。しかしながら、仮に指定事業者の広告モデルがファーストパーティ・データを利用するものである一方で、個別アプリ事業者がサードパーティによる広告モデルを採用し、サードパーティにデータを送信するものであるような場合には、プライバシーの観点から、表示に差異が認めることには合理性がある。このような場合には、「スマートフォンの利用者に係る情報の保護の観点からのリスクに差異がない」とはいえないことに注意を要する。
多くのユーザーは、自分が意識的に利用するサービスについては、そのサービス提供者にサービス利用に関するデータを収集され利用されることを通常認識しているが、他方で、自らアクセスしたつもりのないサードパーティが様々なデータを収集し利用することは想定していない。また、ファーストパーティはユーザーが選択してそのサービスを利用する相手方であるため、自身のデータを取得され、利用されることがあるかもしれないという一定限度の認容・信頼があるのに対して、サードパーティについては、ユーザーとしてはその存在を認識しておらず、そもそも自身のデータを預けることについての認容も信頼も存在しない。
したがって、サードパーティ・データを利用する個別アプリ事業者の広告モデルについては、リスクを強調する表示がなされ、ファーストパーティ・データを利用する指定事業者の広告モデルについて肯定的な表示がなされるとしても、そのような表示は、ユーザーのプライバシー保護の観点からは合理的なものであるといえる。
このような指定事業者による表示は、わが国においてはむしろ合理的でありかつ必要性が高い。なぜなら、わが国において、ユーザーのIDとなるcookieや広告IDといった情報は個人情報として法規制の対象になっておらず、その取得・利用については、法制度上、わずかな制約しかないからである。この点において、わが国は、cookieや広告IDを個人情報として正面から法規制の対象とする欧米とは異なる特質があるというべきである。2022年の電気通信事業法で採用された外部送信に関する規制は、ウェブサイトやアプリがユーザーの情報をサードパーティに対して外部送信する際には、そのことを通知公表しなければならないとするルールであるが、その対象は電気通信事業者を営む者に限られている。このような状況下では、サードパーティによるトラッキングについて指定事業者が「リスクを強調した否定的な説明」を行うことには消費者の権利保護のため一定の合理性があるというべきである。
3.正当化事由に係る考え方のうち「スマートフォンの利用者に係る情報の保護」について(847行以下)
指針案は、スマートフォンの利用者に係る情報の保護について、以下のように述べる。
「具体的には、個人情報の保護に関する法律(中略)の規定や電気通信事業法(中略)の利用者情報に係る規定など現行法令で求められている対応のほか、現行法令の趣旨を踏まえたようなスマートフォンの利用者に係る情報の保護を行うための対応も含まれる。 そうした現行法令で求められている対応又は現行法令の趣旨を踏まえたようなスマートフォンの利用者に係る情報の保護を行うための対応の例としては、・ スマートフォンの利用者からの同意を得ずに、広告の配信及び表示を目的とした当該利用者に係る情報(例えば、広告ID、端末ID、サードパーティクッキー)を取得するなどの行為を防ぐための措置を代替アプリストアに求める対応(中略)などが含まれる。」
この記述は妥当なものであるが、「現行法令で求められている対応」には、ここに挙げられた公法上のもののみならず、民事のプライバシー侵害にならないようにすることも含まれるため、その点を加筆すべきである。また、広告配信を目的として利用者から取得する情報には、「例えば、広告ID、端末ID、サードパーティクッキー」のように識別子のみが例示されているが、これらに加え、ウェブの閲覧履歴やアプリの利用に関する情報を例示に含めることが望ましい。
4.代替アプリストアの利用について(1058行以下【想定例39】)
指針案は、以下の場合は、通常、正当化事由があるとは認められないとする。
「スマートフォンの利用者が代替アプリストアのダウンロード及びインストールを行おうとする際に、いずれの代替アプリストアに対しても審査等を行うことなく一律に、指定事業者が、当該代替アプリストアはスマートフォンの利用に係るサイバーセキュリティの確保やスマートフォンの利用者に係る情報の保護の観点から安全ではないことから利用を控えるように促す旨の警告表示を行うこと。」
警告表示の不当性を問う前に、そもそも審査等を行っていない代替アプリストアが市場投入されていること自体が、サイバーセキュリティの確保や利用者情報の保護の観点からは妥当ではない。仮に、審査を行わない代替アプリストアが市場投入されるのであれば、審査が行われていないことやそのため安全性の保障がないことを警告的に表示することは当然であって、何ら問題がないというべきである。
この問題については、むしろ何らかの審査の前置を必須としたうえで、審査手続きを公正に実施しないことや審査を不当に遅延することが法違反になるという考え方をとるべきである。
この点、OS機能に関する想定例64は、多数の事業者については必要な審査を行いつつも一部の事業者については恣意的に必要な審査を行わないことを問題視しており、ここでも想定例64のアプローチをとるべきではないかと思われる。
5.OS機能の利用に関する想定例の記載について(1438行以下【想定例62】)
指針案は、正当化事由がある場合である想定例62において、「当該API等に係る利用規約において、個人情報保護法の規定や電気通信事業法の利用者情報に係る規定など現行の法令の趣旨に反する形でスマートフォンの利用者に係る情報を取り扱うことを制限すること。」と記載している。この記載は妥当なものであるが、「現行法令」には、個人情報保護法や電気通信事業法といった公法のみならず、民事のプライバシー侵害に係るルールも含まれるため、その点を加筆すべきである。
6.標準設定に係る措置について
(1)基本的考え方について(3004行から3022行まで)
標準設定を容易に切り替えることができるようにするというスマホソフトウェア競争促進法12条の趣旨は十分理解できるが同条において指定事業者に求められる措置等については、同法7条、8条の正当化事由が規定されていない。しかしながら、ここにおいても正当化事由の趣旨は等しく妥当すべきことは明白であるから、「(1)基本的考え方」(3004行以下)の末尾3022行の後ろに、「なお、ここで指定事業者に求められる措置等についても、正当化事由に係る考え方(3(1)ウ)は考慮されるものである」等の文言を加筆すべきである。
(2) 選択画面における選択肢の表示 (3115行目から3136行目まで)
選択画面における選択肢について、客観的・合理的基準に照らして利用者に係る情報の保護に配慮したもののみを選択肢とすることは、規則第28条第2項第1号イで要求された措置を満たすものといえることを加筆すべきである。なぜなら、同号イにおいて指定事業者が求められるのは、選択画面において、スマートフォンの利用者における選択の機会を確保する観点から客観的かつ合理的な選定基準に基づき選定された複数の個別ソフトウェアが選択肢として表示されるようにすることであるところ、上記のような選択肢の表示はまさに「客観的かつ合理的な選定基準に基づく選定」といえるものだからである。
(3)選択肢にかかる表示事項(指針案 3159行目から3171行目)
表示事項について、外部送信の有無や内容その他のスマートフォンの利用者に係る情報の保護に関する客観的・合理的な説明・注意を加えることは、規則第28条第2項第1号ハの観点からは許容されることを加筆すべきである。なぜなら、同号ハにおいて、指定事業者が求められるのは、選択画面における選択肢の表示の順序その他の選択画面の表示が、スマートフォンの利用者の選択を阻害するものでないことであるところ、利用者の情報の保護に関するこのような説明・注意は、スマートフォンの利用者の合理的な選択を支援するものであって、選択を阻害するものではないからである。
以上